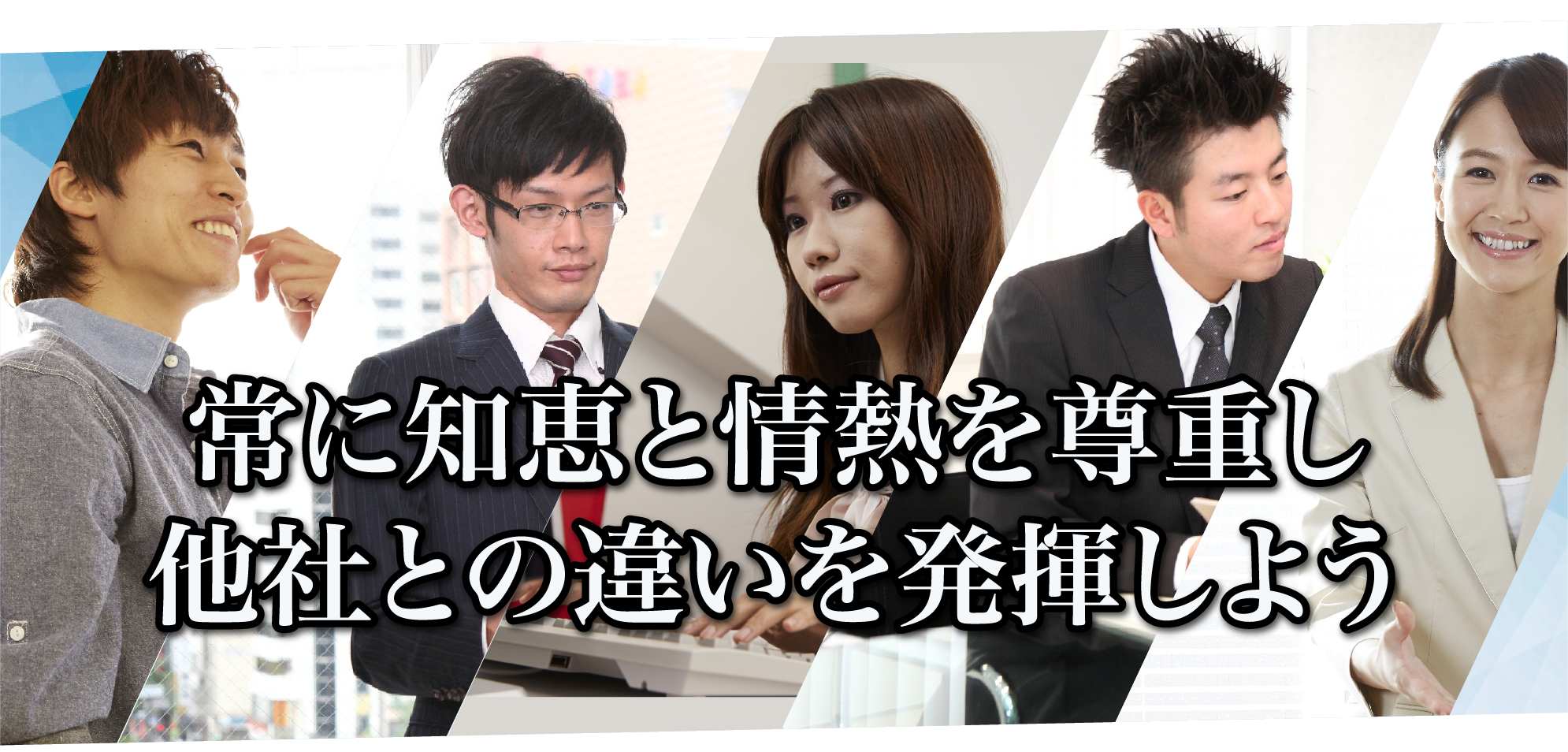
採用情報
RECRUIT
募集要項(2025年度 新卒採用)
| 募集対象 | 2025年3月に卒業(修了)見込みの方 (既卒3年以内応募可) |
| 募集職種 | 製造職 |
| 給与 |
大卒 月給201,000円 高卒 月給170,000円 |
| 手当 | 通勤手当(上限50,000円まで) |
| 給与改定 | 年1回(4月) |
| 賞与 | 年2回(7月、12月) |
| 勤務地 | 栃木工場または埼玉工場 |
| 勤務時間 | 8時20分から17時30分 (休憩時間70分) |
| 休日 | 週休2日制(当社カレンダーによる) GW・夏季・年末年始・有給・慶弔など (年間休日117日) |
| 福利厚生 | 社会保険完備、永年勤続表彰、社員持株会など |
| 社内制度 | 退職金制度、育児・介護休業制度、時短正社員制度など |
| 教育制度 | 新入社員研修、職能別研修など |
| 選考内容 | 書類選考、面接、適性検査など |
| お問い合わせ |
【栃木工場】 総務部 担当:坂本 028-667-6451 【埼玉工場】 総務部 担当:諸橋 042-989-1235 |
※随時工場見学を行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
テレビ埼玉「彩の国就活天国!!」
で紹介されました
社員インタビュー
INTERVIEW

製造部 入社2年目
インフェックで働くと決めたきっかけ
クルマに興味があったのとモノを作ることが好きだったからです。インフェックではまだ市場に出ていないクルマの部品を作ることに魅力を感じ、携わりたいと思いました。
今の仕事の内容
プレス工程から上がってきた部品および、レーザー加工機で切断した部品の仕上げをして次工程の検査係に入れるまでの工程作業をしています。また、溶接技能者をめざし毎日 時間を決めてアルミ溶接技術の習得に取り組んでいます。
やりがい・楽しさを感じるとき
新しい仕事を教えてもらったとき、最初はうまくできなかった作業ができるようになったときにやりがいと楽しさを感じます。

業務係 入社2年目
インフェックで働くと決めたきっかけ
ビジネススクールの紹介で会社訪問した際、試作車の製造という常に新しい取り組みを行っており、日々新鮮な発見や驚きを感じられる職場に魅力を感じました。そこで、学んだスキルを生かし、事務職として周囲の方々のサポートをしていきたいと思い志望しました。
今の仕事の内容
私の所属する業務係は、女性を中心とした様々な専門職の方が仕事をしており、私はその中で、社内の原価管理をするための資料を日々作成しております。製造の課題や問題点の早期発見につなげるため、正確な資料を出せるよう努めています。
やりがい・楽しさを感じるとき
多種多様な仕事を行う部署のため、互いに協力やサポートを必要とし、幅広い知識を学ぶことができます。自分の仕事をしているだけではできない経験が、スキルアップにつながり、やりがいを感じています。

